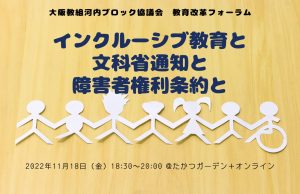ウリカラゲモイムとやおきょうそ

毎年11月、八尾市「ひゅーまんフェスタ」でのとりくみの1つ、ウリカラゲモイム。
ウリカラゲモイムって何?どんな人達がやっているの?
実は、やおきょうそが深く関わっているこのとりくみについて、少し歴史的なことも含めて、記事にしてみました。
子どもたちの教育を受ける権利、とりわけ、被差別の立場にあった子どもたちに必要な教育の発展を願ってきたやおきょうその先達のとりくみを簡単にではありますが、まとめています。
少しお時間をとって、ぜひとも最後まで読んでください!
「ウリカラゲモイム」のスタートは、やおきょうそのとりくみから
在日韓国朝鮮人の子どもたちは、戦後30年以上たっても、自己の出自を隠すなど、アイデンティティの形成に苦しんでいました。そんな1981年、やおきょうそは、当時の八尾市に住む1200人をこえる在日韓国・朝鮮人児童・生徒に向けたサマースクール(現在のオリニマダン)のとりくみを始めます。このサマースクールは、多くの組合員の想いや地域で在日韓国・朝鮮人の青年がたちあげたトッカビ子ども会の全面協力によって成功をおさめました。
1982年、サマースクールの発展として、韓国・朝鮮人児童生徒とそのなかま約1000人が市民ホールに集い、歌と踊り、演劇などで民族的連帯感となかまづくりをすすめるとりくみが始まります。それが現在のウリカラゲモイムにあたる「フェスティバル 韓国・朝鮮の歌と踊り」です。
つまり、オリニマダンもウリカラゲモイムも当時の組合員の方々の反差別の運動の中から生まれたやおきょうそのとりくみだったのです。
在日外国人教育の推進
1988年、12月市議会において、2つの決議が採択されました。一つは、「在日外国人教育に関する基本方針策定に関する決議」であり、もう一つは「中国帰国者の自立・定着へ向けた予算措置に関する意見書」でした。
「在日外国人教育に関する基本方針策定に関する決議」は、やおきょうそが10年来運動をすすめ、策定を求めてきたことがようやく実を結んだもので、全会一致で採択され、八尾の在日外国人教育の推進にとって大きな一歩となりました。
また、中国帰国の子どもたちやその親が増える中で、「中国帰国者の自立・定着へ向けた予算措置に関する意見書」が採択されたことは、きわめて大きなことでした。府教委も、1989年度公立高校入試で、中国帰国生徒の時間延長措置を決定しました(ベトナム人生徒にも援用)。
1990年5月7日、念願の「八尾市在日外国人教育基本方針」が策定され、記念レセプションには、各界から多くの人が集まり、この間の苦労と喜びを分かち合いました。
新しい教育の創造へ
1990年の「八尾市在日外国人教育基本方針」の策定を受けて1992年7月10日に「八尾市在日外国人教育研究会(八外研)」が発足しました。これは、韓国・朝鮮人・中国帰国・ベトナム渡日の子どもたちが多数在籍する八尾市の学校園にとって、在日外国人教育を進めるためのセンターが誕生したということです。
やおきょうそのとりくみから八外研のとりくみへ
こうして、やおきょうそのとりくみとしてスタートしたオリニマダンやウリカラゲモイムは、これまたやおきょうその運動の成果として設立された八外研に引き継がれていくことになります。今では、この2つのとりくみには、八尾市に住む、様々なルーツの子どもたちが集ってきています。
見に来てくれた担任の先生の前で張り切って自分の文化の発表をする子ども。生活にいっぱいいっぱいで、なかなか自分の文化のことを子どもに伝えられない中で、自分のルーツの踊りを生き生きと踊る姿に涙する保護者。
このとりくみは八外研が中心になってとりくみをすすめ、八尾の教育現場にいる一人ひとりの先生たちによって支えられています。